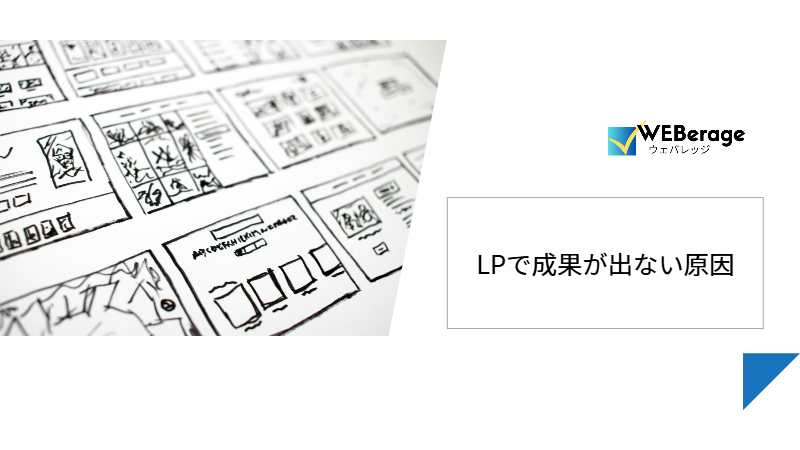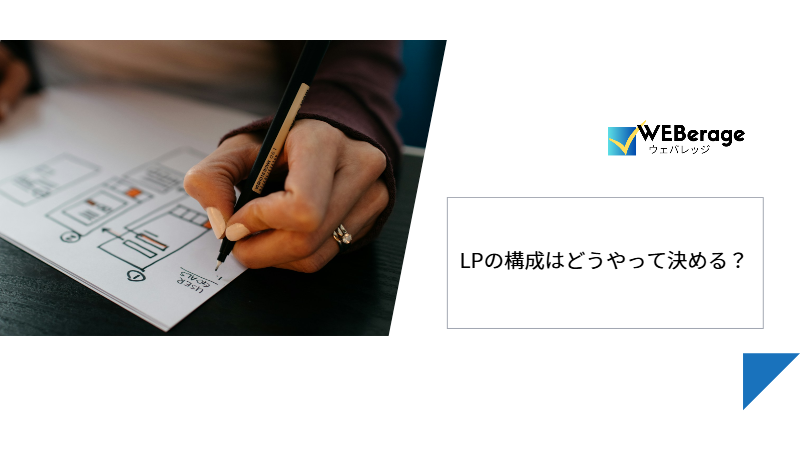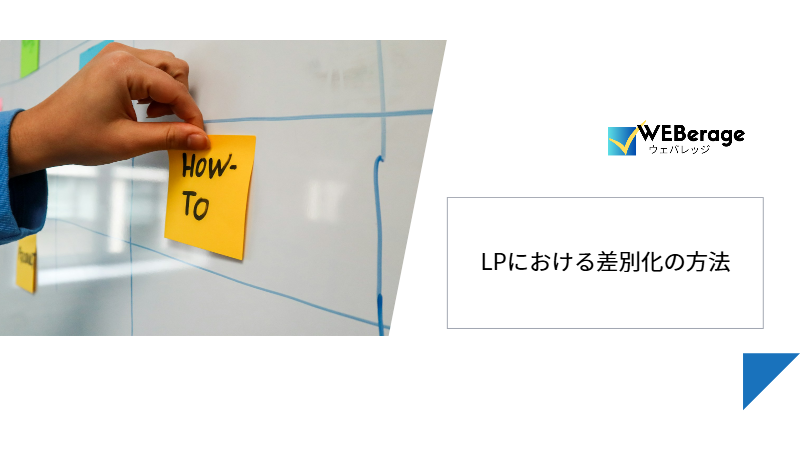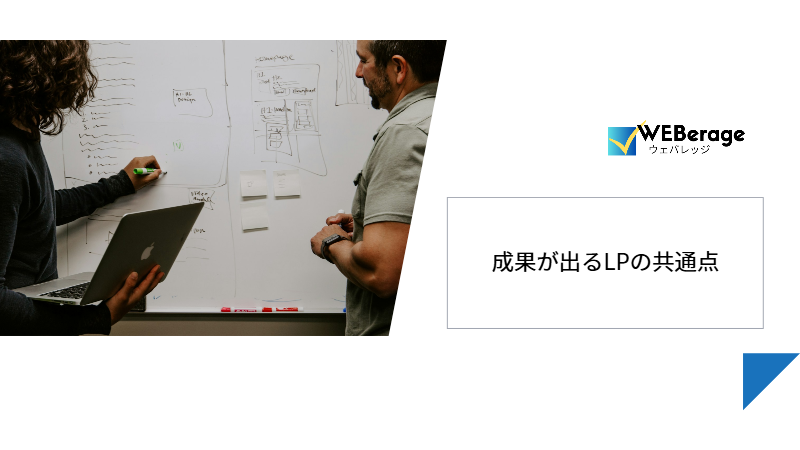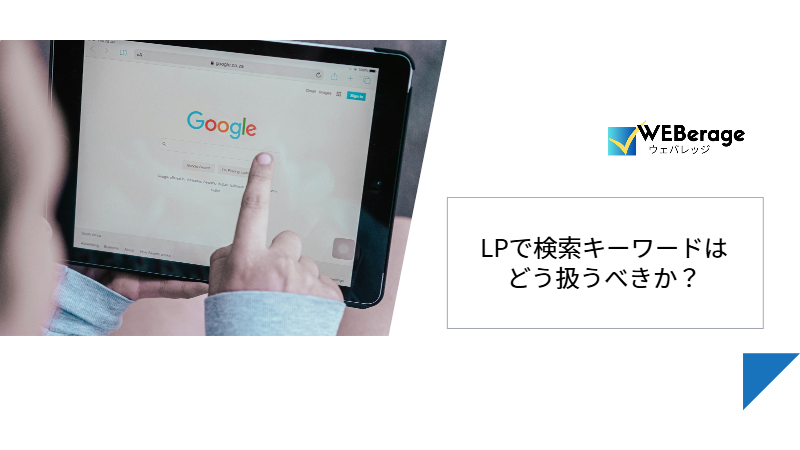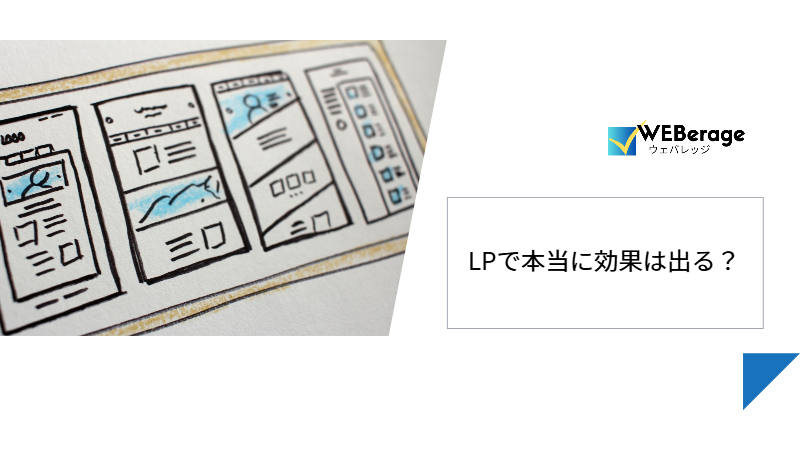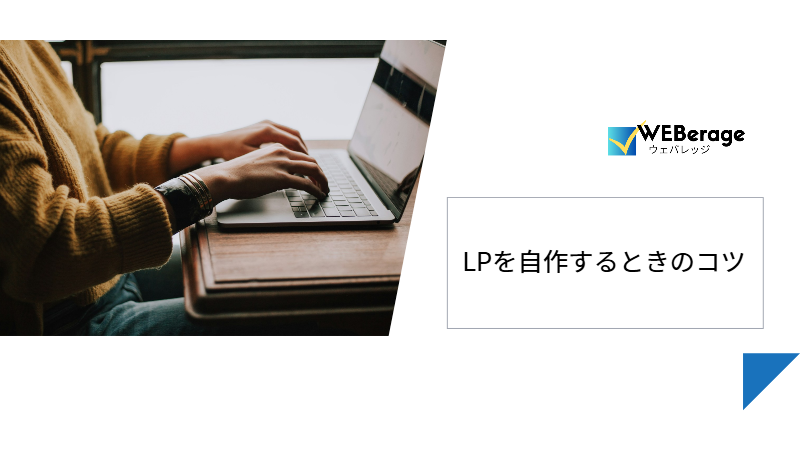LPの長さは重要じゃない?効果を出すために必要なのは「ストーリー設計」
「LPって、長ければ長いほうがいいんですか?」
このような質問をいただくことがあります。
LPにとって重要なのは長さそのものではありません。
LPの成果を出すために必要な情報がしっかり盛り込まれていれば、長くても短くても構わないのです。
つまり、長さは結果であって目的ではないということ。
大切なのは「どんな情報を」「どんな順番で」「どんなふうに見せていくか」というストーリー設計です。
LPは読まれない前提で考える
LPは広告や営業ツールとして使われるものなので、基本的にはしっかり読まれません。
読者は興味のあるところだけを拾い読みして、飽きれば離脱します。
実際に、あなた自身もLPを読んでいて「長すぎるな」と感じて離脱した経験があるのではないでしょうか?
LPは最初から最後まで丁寧に読まれるものではなく、飛び石のように必要なところだけ読まれると考えて設計する必要があります。
そのため、読者が必要とする情報を、必要なタイミングで届けることが何よりも重要になります。
「どんな情報を、どんな順番で並べるか」を考えるのがストーリー設計
ストーリー設計とは、ターゲットがLPを読み進めていく流れの中で、どの情報をどの順番で伝えるかを決めることです。
たとえば、LPを見たターゲットが「この商品いいかも」と思ったあと「どんな良いことがあるの?」「安心できるの?」という疑問が湧いてきますよね。
そのタイミングで商品の詳細情報やユーザーの声などを提示することで、安心感や信頼感を与え、さらに読み進めてもらい、最終的には成果(問い合わせ・購入)へとつなげていくことができます。
このように、ターゲットの心理の流れに合わせて、情報を順番に届けていくのがストーリー設計です。
ストーリー設計の進め方
まずは、ターゲットが商品・サービスについて「知りたい」と思っていることを大まかに洗い出しましょう。
例:ダイエット向けヘルシー弁当のLP
ターゲット:美容や健康に気を遣う30代女性
この場合、以下のような情報が求められていると考えられます。
- お弁当を頼むメリット
- お弁当の中身(例:1食あたりのカロリーや栄養バランス)
- 食材の安全性(添加物・保存料など)
- プランや料金体系
- 利用者の声(ビフォーアフター)
- 実績や販売数、信頼性に関わる情報
そして、それぞれの情報に対して「読者が次に抱く疑問」を想定し、それに答える形で情報をつなげていきます。
たとえば、お弁当の中身を紹介したら、次は「それってどれくらいの頻度で変わるの?」「食材の鮮度は?」という疑問に答える、といったようにです。
設計図をつくって、客観的にチェックする
次に実際にLPを作る前に「伝えることの流れ」を設計図として書き出してみましょう。
まずはセクション(情報の塊)を決めます。
例)
- この商品が生まれた背景
- 商品の特徴と魅力
- こんな人におすすめ
- 実際の中身や内容紹介
- 安心・安全への配慮
- ユーザーの声
- 価格・購入の流れ
- よくある質問
- 行動を促すメッセージ(CTA)
次に、各セクションに盛り込む情報を、箇条書きで書いていきます。
各セクション3~5行ぐらいで構いません。
出来上がったら、この設計図をターゲットの気持ちになって上から順番に読んでみてください。
途中で違和感を覚えたり、集中が途切れたり、読み進める気が失せたりしたら、そこはストーリーのどこかに無駄や過剰な説明があるということです。
詰まったポイントを修正すれば、ストーリーの設計図が完成します。
不要な情報を見極めるには「ターゲット目線」がすべて
LPでやりがちなのが、「あれもこれも伝えたい」と情報を詰め込みすぎてしまうこと。
これは、ターゲットよりも自分の「伝えたい気持ち」を優先してしまっている状態です。
でも本当に重要なのは「ターゲットが知りたいこと」だけを的確に、わかりやすく届けること。
そのためにも、ターゲットの属性とニーズ、読み進めるときの心理変化を理解することが大切です。
まとめ:LPの長さより、読者を導く「設計」が大事
LPの成果は、長さで決まるのではなく、ターゲットを成果へと導くためのストーリー設計で決まります。
「どんな情報を」「どんな順番で」「どうやって届けるか」。
この設計をしっかり組み立てることで、無駄のない、読まれるLPができあがります。
読み手の気持ちになって、迷わせずに自然と行動につながるような流れをつくることが、成果の出るLPの条件です。
LPの設計に悩んでいませんか?
「どこまで情報を入れるべきか分からない」
「流れがうまく作れない」
そんなお悩みがある方は、お気軽にご相談ください。
ターゲット心理をベースにした、成果につながるストーリー設計をご提案します。