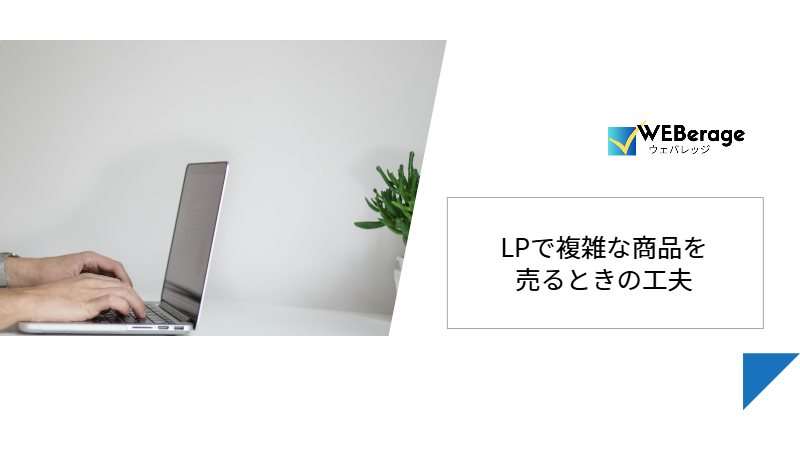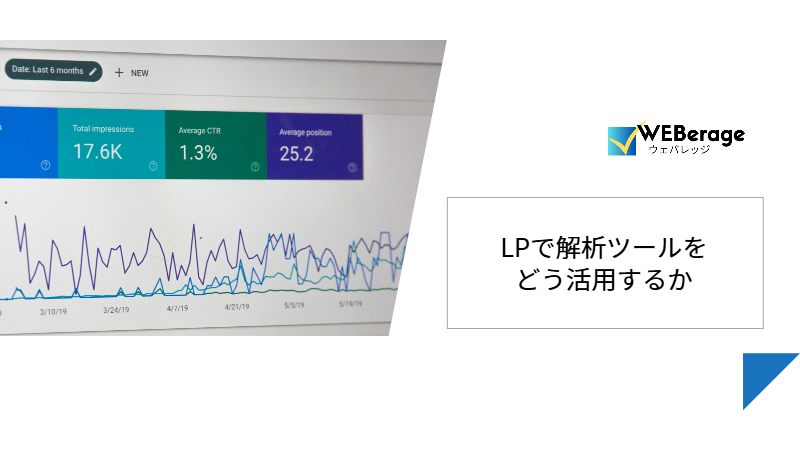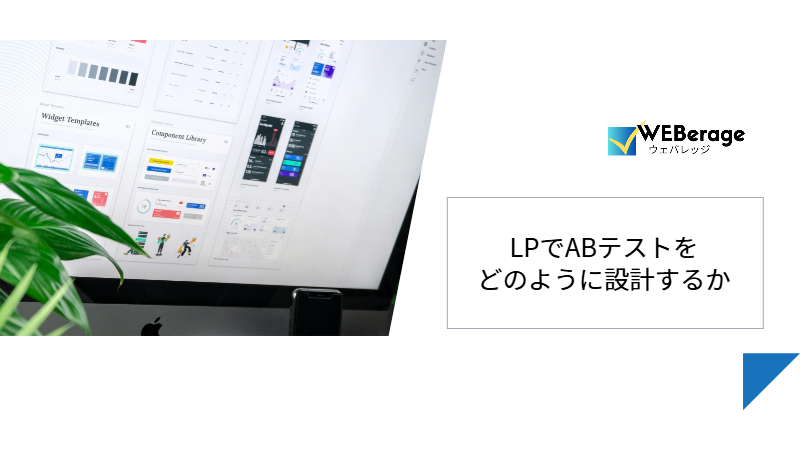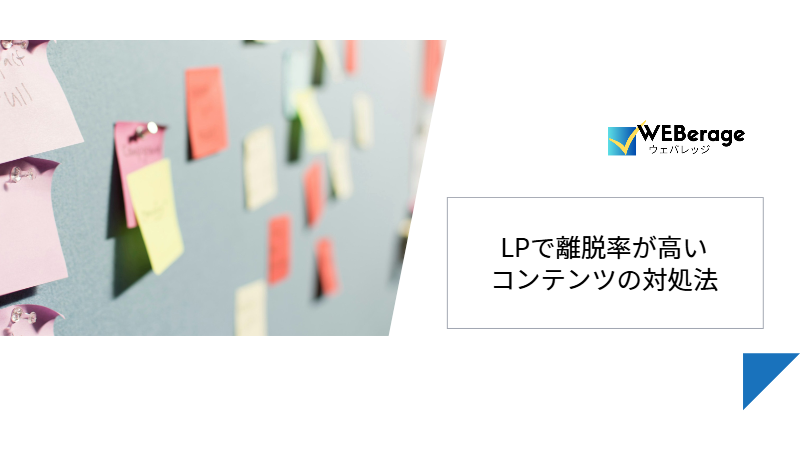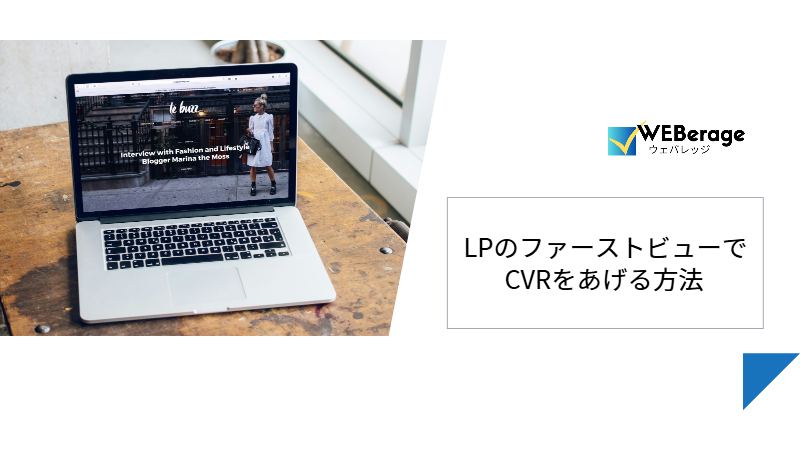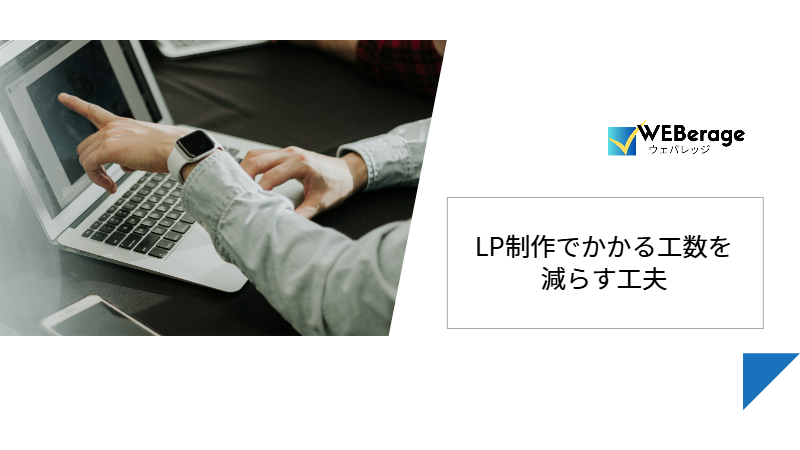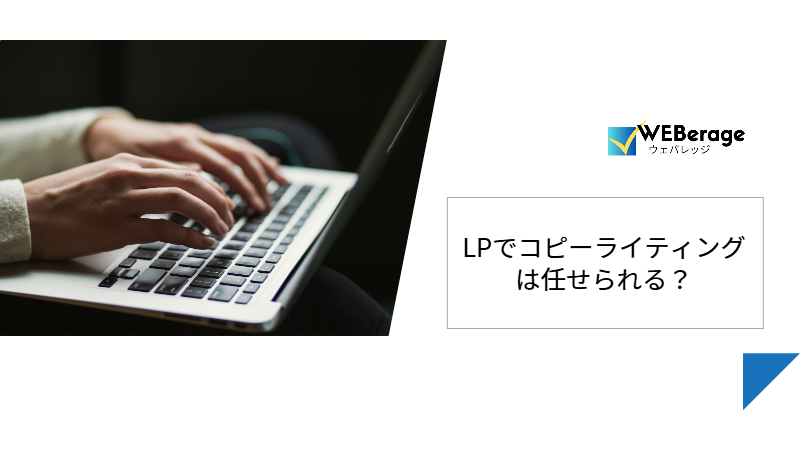LPで強みが複数ある場合、どうやって構成に優先順位をつけますか?
LP(ランディングページ)をつくるとき、「どのUSP(独自の強み)を前面に出せばよいか分からない」というご相談をいただくことがあります。
強みが複数ある場合、すべてを伝えたいという気持ちが先立ち、結果として「結局何が一番すごいのか伝わらないLP」になってしまうことがあるので注意が必要です。
強みがたくさんあること自体は素晴らしいことです。
そこで大切なのは、それらをどう見せるか・どう整理するかです。
まずは全部活かす前提で考える
「優先順位をつけなきゃ」と思うと、どうしても強みを削る方向に意識が向いてしまいます。
ですが、最初は削らず、全部を活かす方法を考えるのが良いスタートになります。
たとえば、「業界特化のノウハウがある」「料金が安い」「対応が早い」といった複数のUSPがある場合、これらをどのようにLP内で整理するかによって、伝わり方も反応率も大きく変わります。
並列に見せる or 順番に見せる:2つの方向性
複数のUSPを扱う際の基本戦略は、以下の2つです。
- 並列に見せる
たとえばファーストビューで「この3つが強みです」と端的に伝えることで、どのターゲットにも満遍なく刺さるようにする - 順番に見せる
ターゲットの関心をひとつずつ育てていく構成。たとえば1つ目のUSPで惹きつけ、2つ目・3つ目で説得力を加える
どちらが良いかは、ターゲットや訴求内容によります。
強みを絞った方がいいケースもある
すべてのUSPを平等に訴求しようとすると、逆に何も刺さらなくなることもあります。
特に、ターゲットが最初に求めているニーズがはっきりしている場合は、そのニーズに直結したUSPをメインに押し出し、他の強みはサブにまわすのが有効です。
商品やサービスの特徴がぼやけてしまう場合は、潔く「このページではこのUSPをメインで伝える」と割り切ることも大切です。
ターゲットのニーズをどう見極めるか
ここで重要になるのが「ターゲットリサーチと分析」です。
強みをどの順番で出すか、どれをメインに据えるかは、誰に何をどのように届けるかという戦略にかかっています。
そのためには、以下のような視点でリサーチ・分析を行う必要があります。
- 顧客が今どんな悩みを抱えているのか
- 他社はどんな訴求で戦っているのか
- 自社のUSPは市場の中でどのような位置づけになるのか
こうしたリサーチを元に、「このターゲットにはこの順番が刺さる」「この層にはこのUSPを最初に伝えるのがベスト」といった判断ができるようになります。
3つの実践的な手法
複数のUSPがある場合、私たちは以下のような手法で構成を決定しています。
① 共通のインサイトを軸にする
3つのUSPに共通して刺さるターゲットの本質的な悩みや課題認識がある場合、それをファーストビューに据えます。
そのうえで、各USPを「その悩みに対する3つの解決策」としてぶら下げていく構成にします。
② LPを複数作る
1つのLPにすべてを詰め込まず、USPごとに訴求軸を変えたLPを3本作成し、広告の出し分けやSEO対策を変えて運用する方法もあります。
これにより、より明確に「誰に、何を、どのように」届けるかを設計できます。
③ A/B/Cテストを実施する
戦略設計の段階から「どのUSPがもっとも響くか」という仮説を複数用意し、A/B/Cテストで反応を比較することも可能です。
部分的な見出し変更ではなく、構成ごと変えた複数パターンでファーストビューやセクションの順番をテストすると、中長期的により高い成果が得られます。
まとめ
強みが複数ある場合でも、適切な設計を行えば情報が散らかった印象にはなりません。
むしろ、適切な順番・組み合わせ・見せ方によって、説得力が増し、反応率が向上します。
弊社では、20ページにわたる戦略企画書をもとに、こうした強みの整理や訴求順の設計を丁寧に行います。
仮説が複数ある場合は、A/Bテストを前提にした構成提案も可能です。
強みが多い企業様ほど、ぜひ一度ご相談ください。
まずは無料相談からお気軽にお問い合わせください
「自社の強みをどう伝えるべきか分からない…」
「いくつかUSPはあるけど、優先順位や伝え方に迷っている…」
そんなお悩みがある方は、ぜひ一度ご相談ください。
無料相談では、お客様の状況やご要望をお伺いし、課題整理やLP設計の方向性をご提案しています。